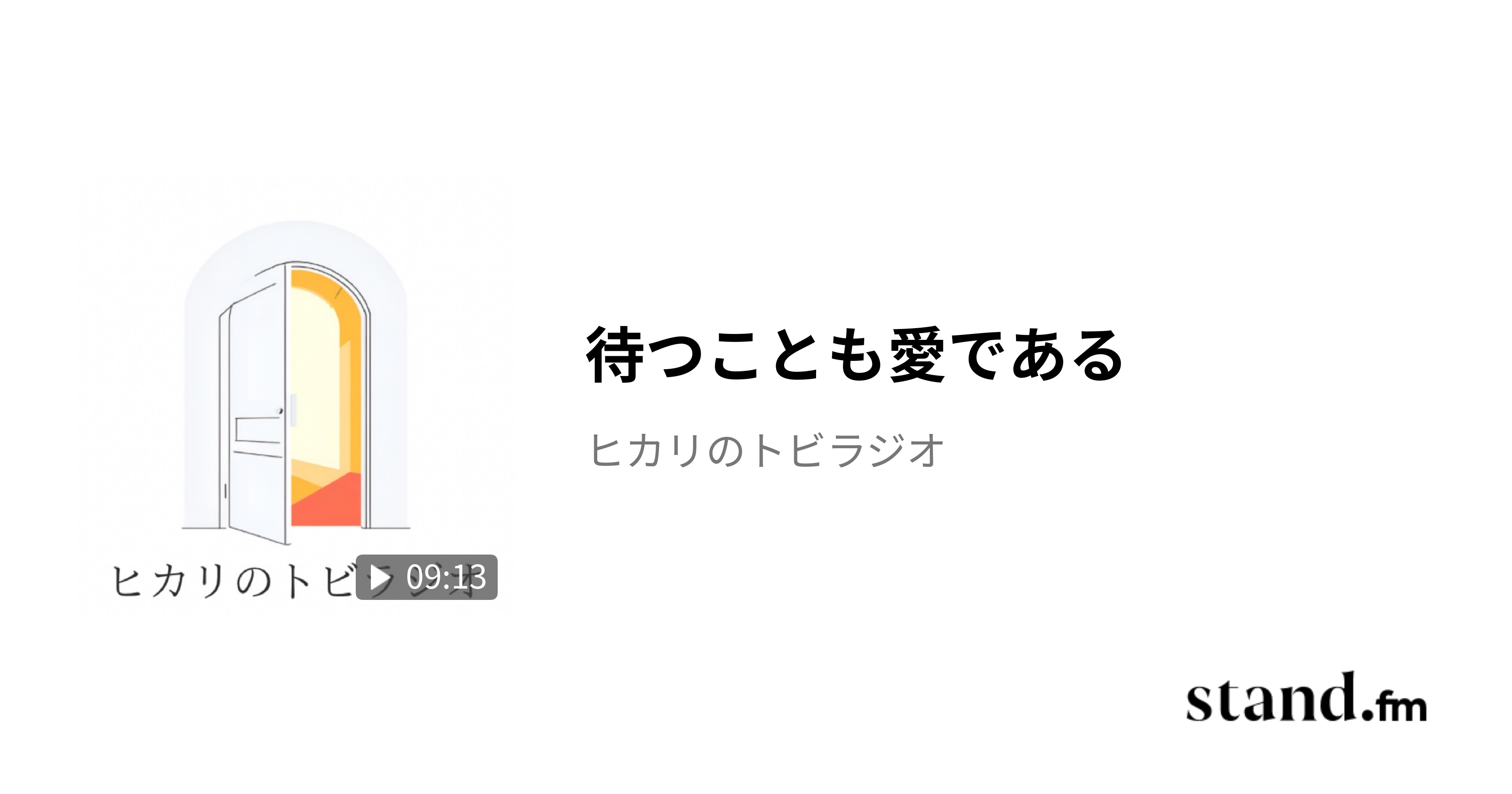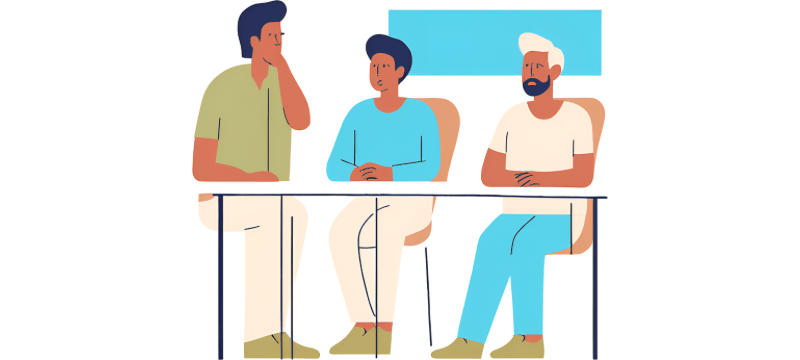年齢を重ねていくにつれて、私たちは人生の先輩になっていきます。
若い人たちや後輩、部下、または自分の子どもたちなどと向き合うことが必然的に増えてくるものです。
それまでは教えてもらう側だったのが、今度は教える側になっていきます。
自分がすでに経験し、学び終えて、通り越してきたことを次の世代に伝えていく立場になっていくわけです。
そのときにすでにできることが増えている自分とまだできないことが多い人たちとの間の隔たりを感じないわけにはいかなくなってきます。
すると、自分よりも若い人たちに対して、次のような思いが出てくるのです。
「どうしてこれが分からないんだろう」
「なぜこれができないんだろう」
すでにそれが身について当たり前になっている者からすれば、理解ができず、イライラさせられるような場面も出てくるかと思います。
そのときに覚えておきたいのが、「待つことも愛である」ということなのです。
待つというのは、相手の成長や気づきを得ることを見守るということです。
私たちは最初から何もかもを悟って、万能に働けるような存在ではありません。
それはやはりそれぞれ自分自身を振り返ってみてもらってもそうだと思うのです。
何年という、何十年という時間を経て、他の人たちよりも少し前を歩いているかもしれませんけれども、自分が同じ立場だったときが、同じように未熟だったときがあるはずです。
そこから学びや経験を積んで、やはり今の自分というものがあるのです。
それを思えば、未熟に思えるような人に対しても裁いて叱責をするのではなくて、昔の自分の姿を重ね合わせるようにして、その成長を温かく見守るということ。
相手ができないこと、理解できないことを針で突き刺すのではなく、その相手の辛さや大変さも受け止めて、時間をかけて待つということです。
それも愛であるということです。
人を育むというのは生半可なことではありません。
労多くして功少なしという言葉もありますけれども、人を育むということは本当にそういう面が多いと思います。
報われることも少ないですし、思った通りにならないということも多いですよね。
それでも待つということ。
それは相手の中にある神性を信じ抜くということでもあります。
どのような立場であれ、環境であれ、人は必ず時間をかけて成長をしていきます。
それは、より善くなっていくということです。
もちろん、それは何もせずに放置しておけばいいということではなく、必要に応じて適切に導くことは欠かせませんけれども、自分の思い通りに操ったり、支配するということでは決してありません。
何を思い、何をするか。
それはそれぞれの自由意志が決めることです。
それを尊重しつつ、待つということ。
そう言葉で言うのは簡単かもしれませんが、待つというのはそんなに容易いことではありませんよね。
それでも相手の成長を、学びを待つということ。
それは神の愛の思いに通じるものでもあります。
神は永遠の時を待たれています。
すべての神の子たちの成長、進化、発展を温かく見守り、育んでいらっしゃる神のお姿というものがあります。
それを見習い、少しでもその思いに近づけるような自分自身であること。
待つことも愛であるということを今回はお伝えしたいと思います。
▼音声配信はこちら